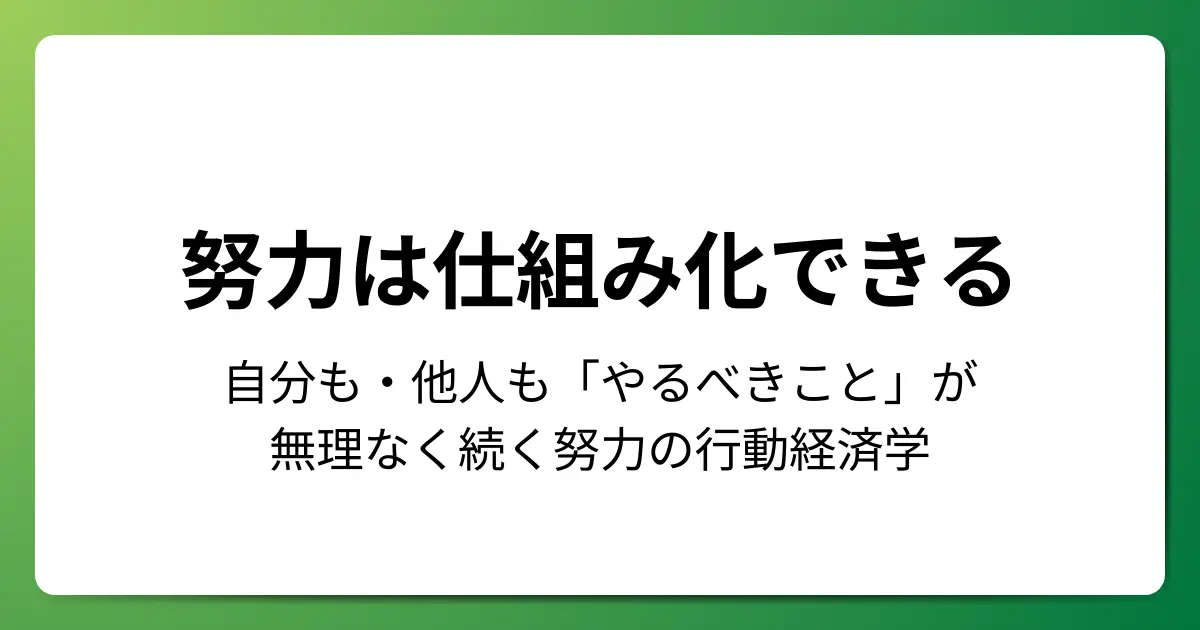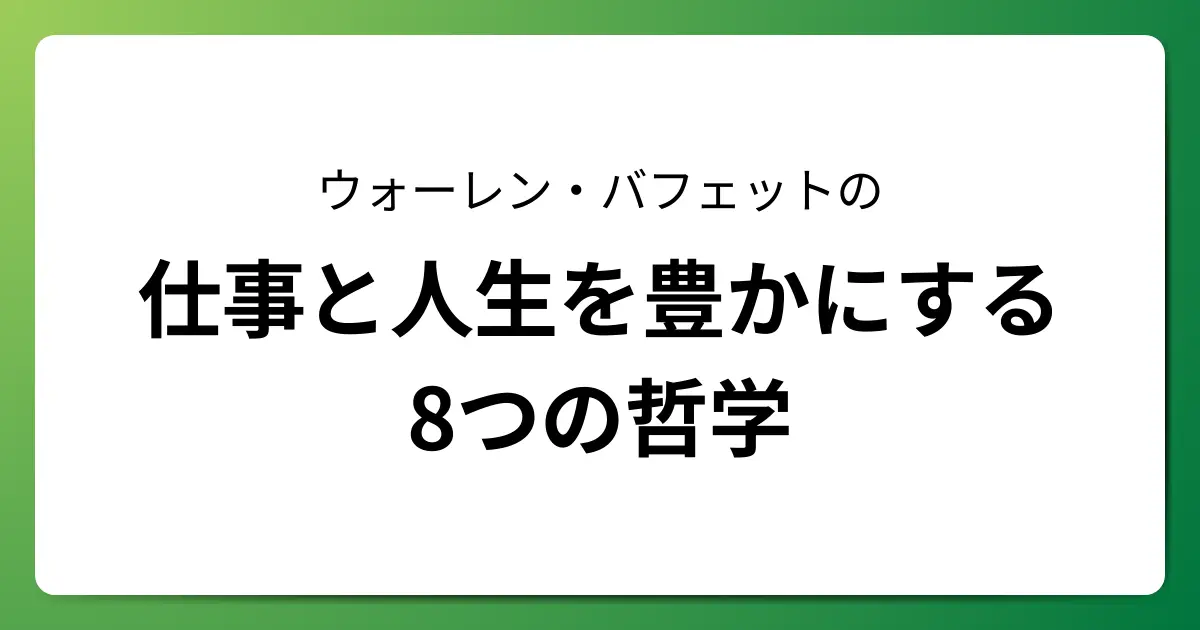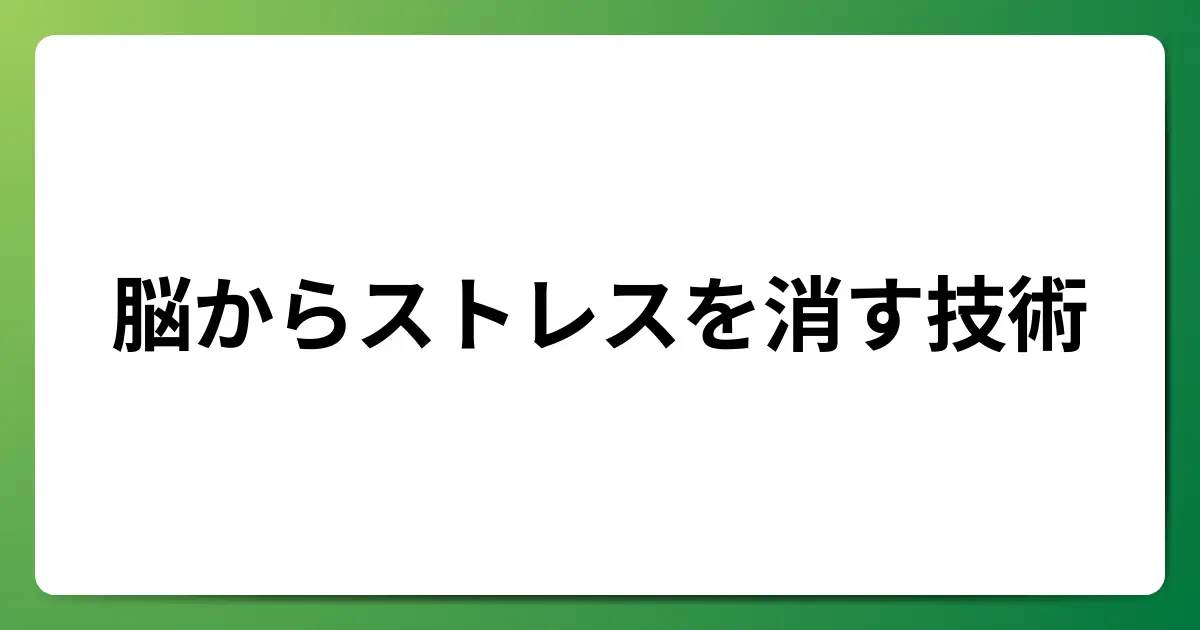この記事は『努力は仕組み化できる 自分も・他人も「やるべきこと」が無理なく続く努力の行動経済学』についての書評です。
『努力は仕組み化できる 自分も・他人も「やるべきこと」が無理なく続く努力の行動経済学』は、山根承子さんの著書。
2024年に日経BPから出版されました。
効率的に習慣化するための仕組みを、理論立てて理解したい方におすすめの書籍です。
本の3行紹介
行動経済学者である山根承子さんの著書。
「努力」という概念を、データと行動経済学の根拠を踏まえて理論立てて解説してくれます。
精神論ではなく、科学的に努力する仕組みを構築したい方におすすめできる本です。
- 第1章:「努力」を行動経済学で考える
- 第2章:「努力が勝手に続く」4つの仕組み
- 第3章:「努力を楽しむ」ことはできるのか?
- 第4章:必要な努力が無理なく続く2つのナッジ
- 第5章:「誘惑」と戦う
- 第6章:【努力しない言い訳】と戦う①「今回は、運が悪かったね」
- 第7章:【努力しない言い訳】と戦う②「(努力しなくても)何とかなるでしょ」
- 第8章:「環境からの悪影響」と戦う
- 第9章:他人からの低い評価に立ち向かう
- 第10章:人はなぜ後悔するのか?
- 第11章:「続ける=よい」「努力=すばらしい」は本当か
個人的な2つの学び
本書を読んで得た、個人的な学びポイントを2つまとめます。
フィードバックよりも大切なこと
会社の面談などでフィードバックをもらう方は多いのではないでしょうか?
期初に目標を立てて、面談の際に「今期どれだけ達成できたか」という内容を話し合ったりしますよね。
ですが、実はフィードバックそのものには、それほど意味はないそうです。
重要なのは、フィードバックの内容を受け止めて、それを目標に反映させることだと、著者は述べています。
つまり、「今回は〇〇だったから、次回は〇〇でやってみよう」というように、自分で適宜改善できること自体が、パフォーマンス向上につながるということ。
自分が主体となって前に進んでいる感覚が、成長には大事なのかもしれませんね。
努力を続けやすくする「ナッジ」の力
選択の余地は残したまま、望ましい選択に誘導するという介入の仕方を「ナッジ」と呼ぶそうです。
ナッジは「肘でそっとつつく」という意味。
強制するのではなく、より良い選択肢にそっと気づかせてあげる、という発想です。
以下のように、日常の中にもナッジを有効活用している例があります。
- 場面
- ホテルで連泊する時
- ナッジの工夫
- 「80%のお客様がシーツとタオルを再利用してくださっています」という札を置く
- 期待される効果
- これを見た利用者に「そんなにたくさんの人が再利用しているなら、自分もしてもいいかな」と思わせる
この仕組みを日常に取り入れることで、普段よりもグッと習慣化しやすくなるのだとか。
例えば、健康的な習慣を身につけるナッジには、以下のようなものがあります。
- 場面
- 職場や駅のエスカレーターやエレベーターの前
- ナッジの工夫
- 「階段を使うと1日約10分運動できます」といったメッセージを貼る
- 期待される効果
- 社員や駅の利用者に自然と体を動かす機会を与えることができる
ちょっとしたことで人の行動は変化するそうなので、私もナッジを有効活用していこうと思います。
感想
行動経済学が専門で、元大学教員でもある山根承子さんによる本。
学術的な観点から、「努力とは何か」「どうしたら習慣化できるのか」ということを説明してくれます。
巷によくある習慣化本と比べると、研究への言及が多めで、全体的にとても論理的です。
物事の仕組みや原因を理解するとやる気がでるタイプの人にとっては、とても相性が良い本になると思います。
一方で、科学的な面からの話が多いので、普通に習慣化する際のテクニックを知りたい人にとっては、ちょっと冗長すぎるかもしれません。
本書はあくまでも「努力を行動経済学で理解する」ための本と考えたほうが、ミスマッチが少なくなりそう。
可能であれば、書店でパラパラと中身を確認するのをおすすめします。
まとめ
この記事では、山根承子さんの著書である『努力は仕組み化できる 自分も・他人も「やるべきこと」が無理なく続く努力の行動経済学』の概要と感想をご紹介しました。
今回ご紹介したもの以外にも、いろいろなヒントが散りばめられた本でした。
習慣化を極めたい方や理詰めで動く方がモチベーションが上がるという方は、ぜひ一度読んでみてくださいませ。