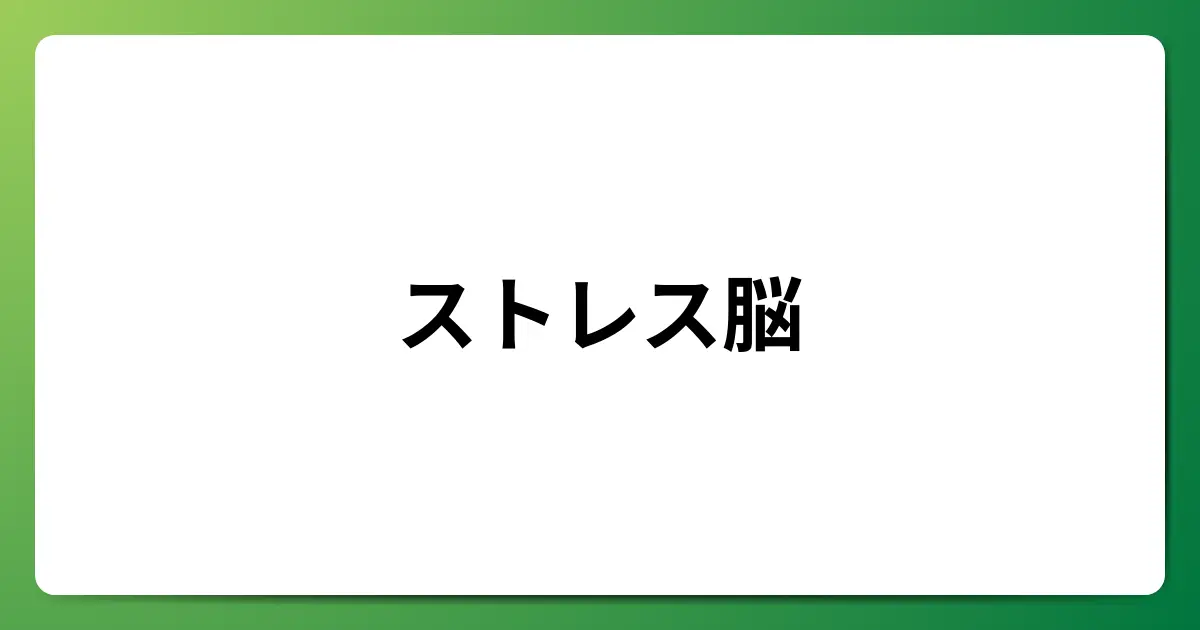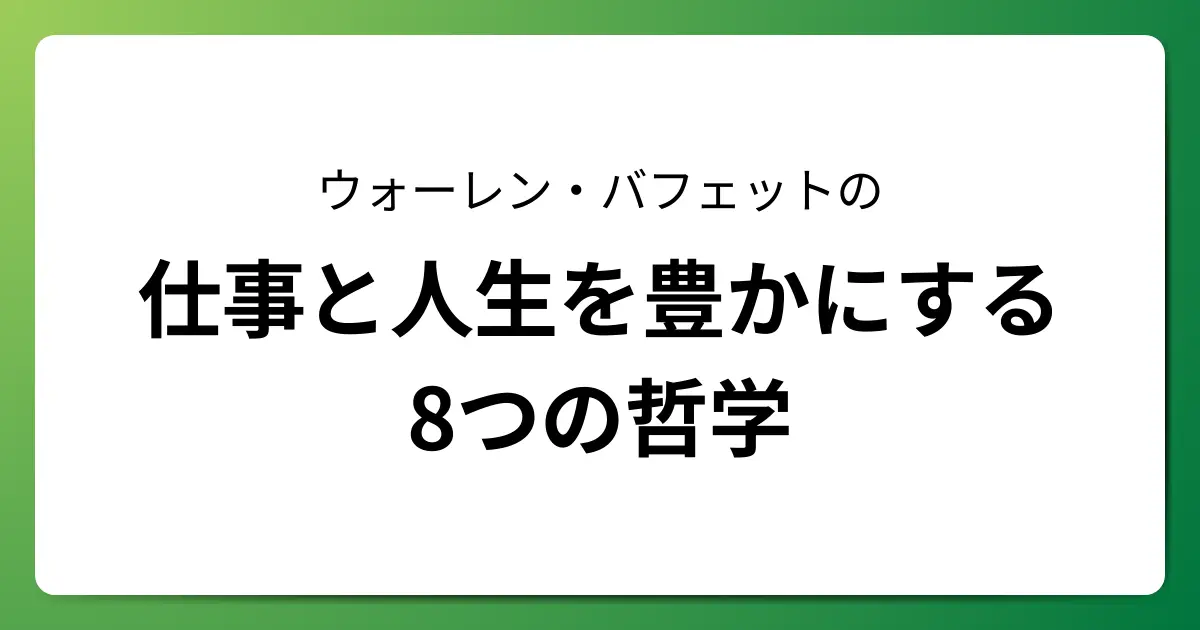この記事は『ストレス脳』についての書評です。
『ストレス脳』は、アンデシュ・ハンセンさんの著書。
2022年に新潮社から出版されました。
脳がストレスを感じる仕組みとその対処法を知りたい方におすすめの書籍です。
本の3行紹介
スウェーデンの精神科医であり、ベストセラーになった『スマホ脳』の著者としても有名なアンデシュ・ハンセンさんの著書。
科学的な観点と人類学的な観点から、人間のストレスに関する仕組みや背景をわかりやすく解説してくれます。
ストレスや不安に苦しむことが多い人に、ぜひ読んでいただきたい良書です。
- 第1章 私たちはサバイバルの生き残りだ
- 第2章 なぜ人間には感情があるのか
- 第3章 なぜ人は不安やパニックを感じるのか
- 第4章 人はなぜうつになるのか
- 第5章 なぜ孤独はリスクなのか
- 第6章 なぜ運動でリスクを下げられるのか
- 第7章 人類の歴史上、一番精神状態が悪いのは今なのか?
- 第8章 なぜ「宿命本能」に振り回されてしまうのか?
- 第9章 幸せの罠
個人的な3つの学び
本書を読んで得た、個人的な学びポイントを3つまとめます。
不安は脳の機能が正常に働いている証拠
不安を感じる際の起点となるのは、脳の扁桃体です。
この扁桃体は「火災報知器の原則」で動くと、アンデシュ・ハンセンさんは指摘しています。
- 本当の危機を見逃さないのであれば、一度くらい間違えても大丈夫、という理論
常に惨事に備えている人間の方が生存率が高かったので、脳は進化の過程で、常に惨事に備えるようになったのです。
脳としては、一度少なく鳴るよりかは、一度多く鳴る方が生存には都合が良いわけですね。
これは生存を考えると便利な機能なのですが、現代のような基本的に平和な時代には、少々過剰なところがあります。
というのも、この警報が頻繁に発生するようになると、いわゆる「不安障害」と呼ばれる状態になり、さらに深刻化してストレスシステムが過剰に作動するようになると、「パニック発作」になってしまうからです。
つまり、パニック状態になるのは脳の機能が正常に働いている証拠なのですね。
私も一時期、「こんなに不安になるなんて、自分はおかしいのではないか」と不安になっていたのですが、脳の正常な機能が過剰に働いているだけだとわかり、少しほっとしました。
メンタルの調子が悪いと微熱になる理由
デンマークで行われた研究では、軽度のうつ状態、疲労感、自尊心の低下などが見られた人たちは、炎症を示す数値がしばしば高いことがわかっています。
特に、うつ状態の患者は体温も高く、微熱状態だったそうです。
アンデシュ・ハンセンさんによると、人類の歴史上、ほとんどの期間、ストレスというのは身体にとって「感染リスクが高まった」という明確なシグナルだったのだとか。
人類の長い歴史で考えると、人間の半数は大人になる前に感染症で亡くなっているからです。
そのため、脳はストレスを受けると、感染リスクが高まったと認識し、身体の免疫系を活発化させます。
免疫系が活発化した結果、体温も上昇するわけですね。
私もメンタル不調に陥っていたときには、いつも37.2~37.3度くらいの微熱が出ていました。
もしも、風邪でもないのに微熱が続いている方がいれば、メンタル不調を疑った方がいいかもしれません。
ストレスに効く運動の条件
ストレスと運動に関する研究は盛んです。
例えば、2019年に発表された研究結果では、毎日じっと座っている代わりに、15分間ジョギングするだけで、うつになるリスクが26%減少することがわかっています。
これは1時間の散歩でも同じ効果が得られるそうです。
また、2020年に発表された研究結果では、心拍数の上がる運動によって、子どもも大人も、不安やPTSDから守られることが明らかとなっています。
特に重要なのは、運動の種類は関係なく、心拍数が上がればOKだということです。
実際、パニック発作のある人は発作が減り、発作を起こしても以前ほど激しくはなくなったとのこと。
以上を踏まえて、アンデシュ・ハンセンさんは週に1時間早足の散歩をおすすめしています。
慣れてきてから少しずつ強度を上げていけば良いそうです。
ちなみに、最も効率的なのは週に2~6時間心拍数の上がる運動をすることで、どちらかというと、2時間寄りのほうが結果は良いそうです。
感想
ストレスからくる不安やうつについて、その仕組みと背景を解説している本でした。
科学的な面からはもちろん、人類学的な観点から、なぜ人間には不安やストレスを感じる機能が備わっているのか、ということを分かりやすく教えてくれます。
人類の進化の歴史の中で言えば、私たちの脳はまだサバンナにいると勘違いしているのだ、という話は興味深かったです。
現代文明の急激な進歩に付随するひずみのようなものが、私たちのストレスや不安という形で表れているのかもしれません。
筆者はそういった諸々への対処法として運動を進めていました。
これも科学的な見地からの提案になっているので、とても納得感があるものです。
運動がいいとは聞いていたのですが、この本を読むことでようやく腹落ちした感じですね。
ストレスに悩まされていたり、現在休職中で不安に苛まれている人は、体調が良いときに一度読んでみてほしい良書だと思います。
「疲れていて活字を読むのは辛い…」という方には、筆者の『メンタル脳』がおすすめです。
本書の内容をもとに、中高生向けにまとめ直されたものダイジェスト版なので、そちらもとても読みやすい良書でした。
まとめ
この記事では、アンデシュ・ハンセンさんの著書である『ストレス脳』の概要と感想をご紹介しました。
孫子も「敵を知り己を知れば、百戦して危うからず」と言っていますが、ストレスや不安を感じる仕組みを理解することで、いざという時の対処方針が定まりやすくなります。
本書では他にもいろいろな対処法や仕組みが紹介されているので、自分に合った方法を取り入れていきましょう。