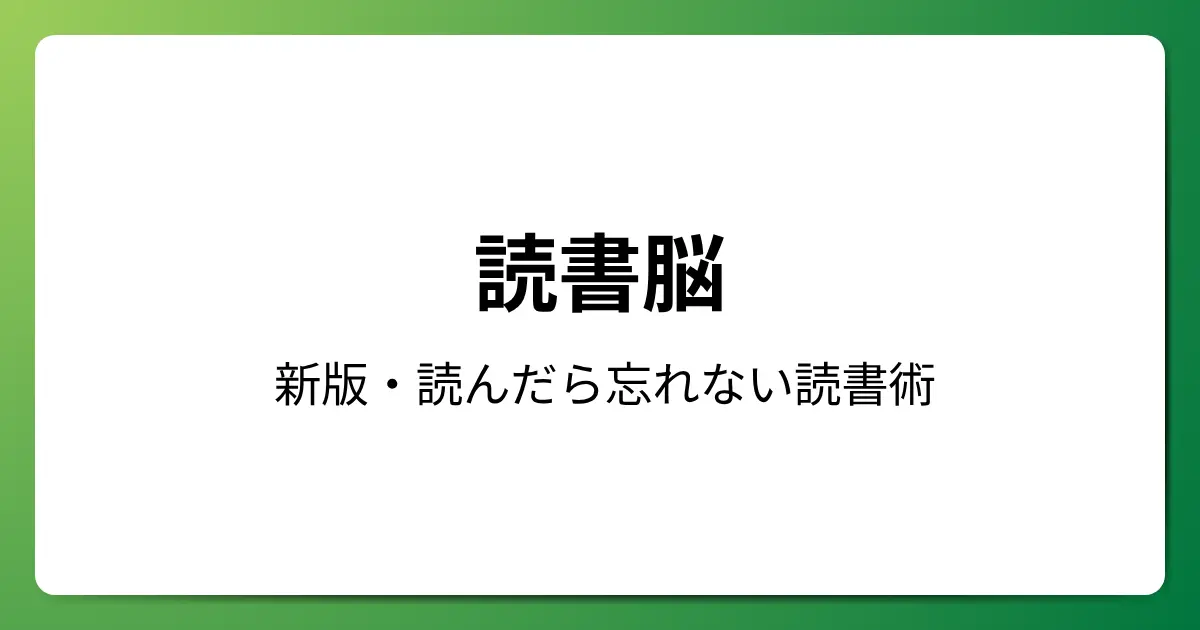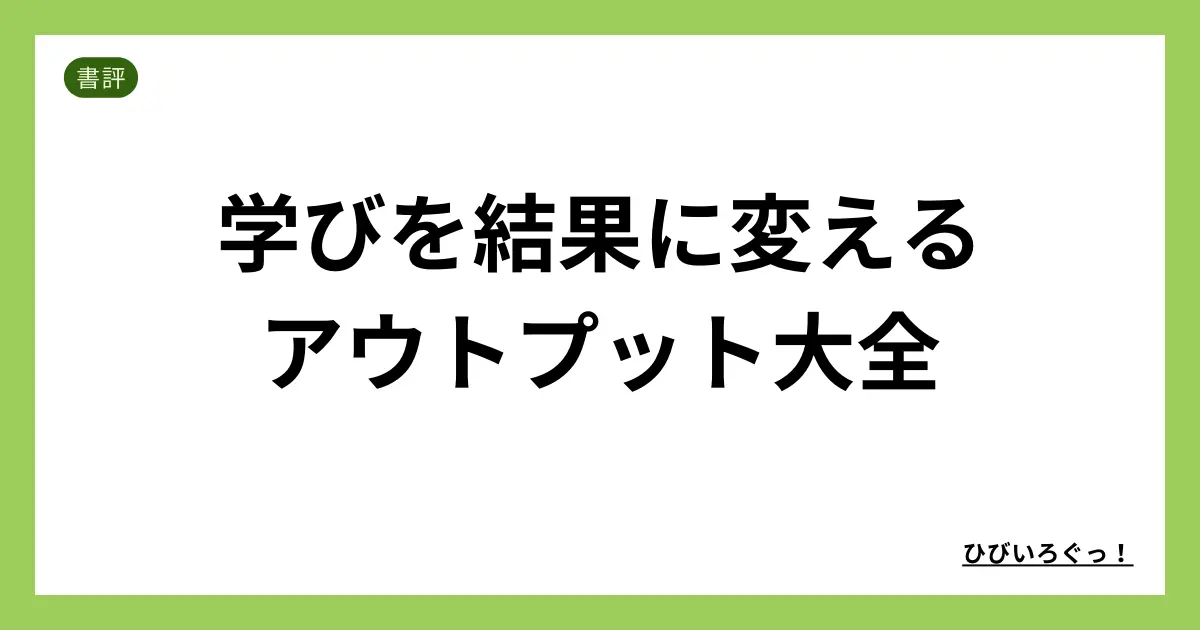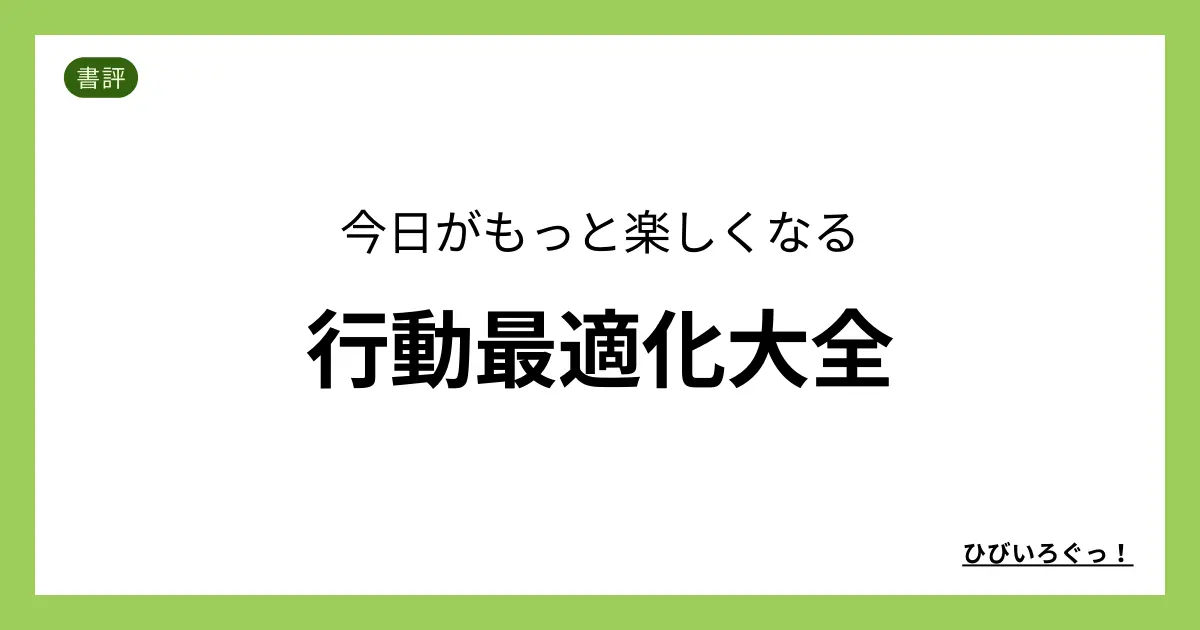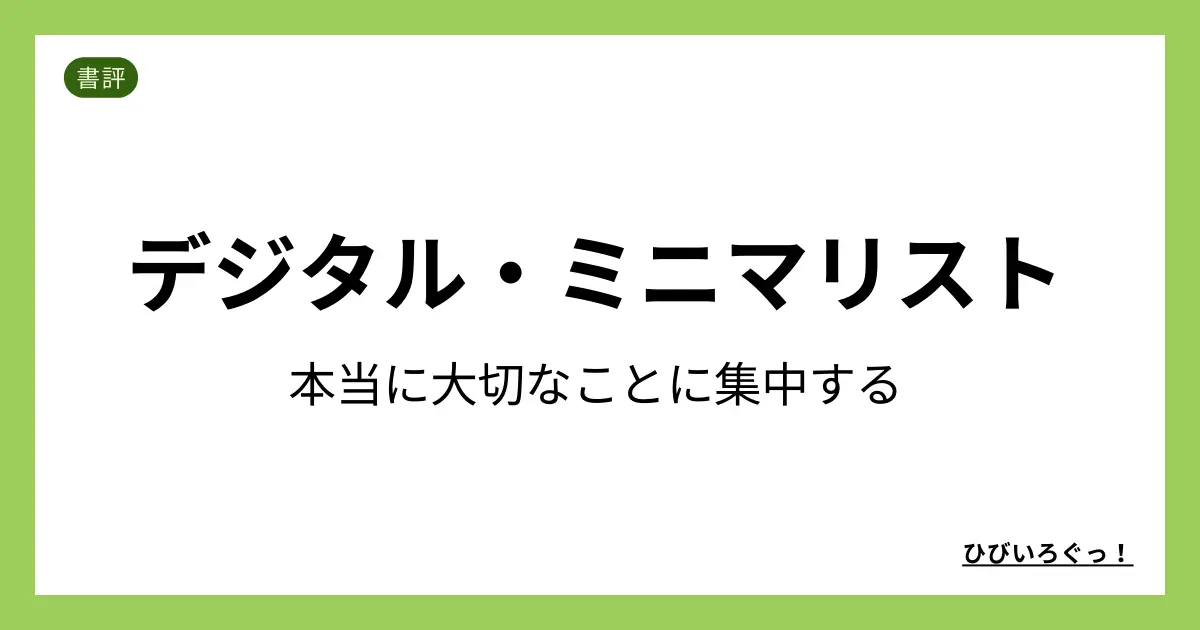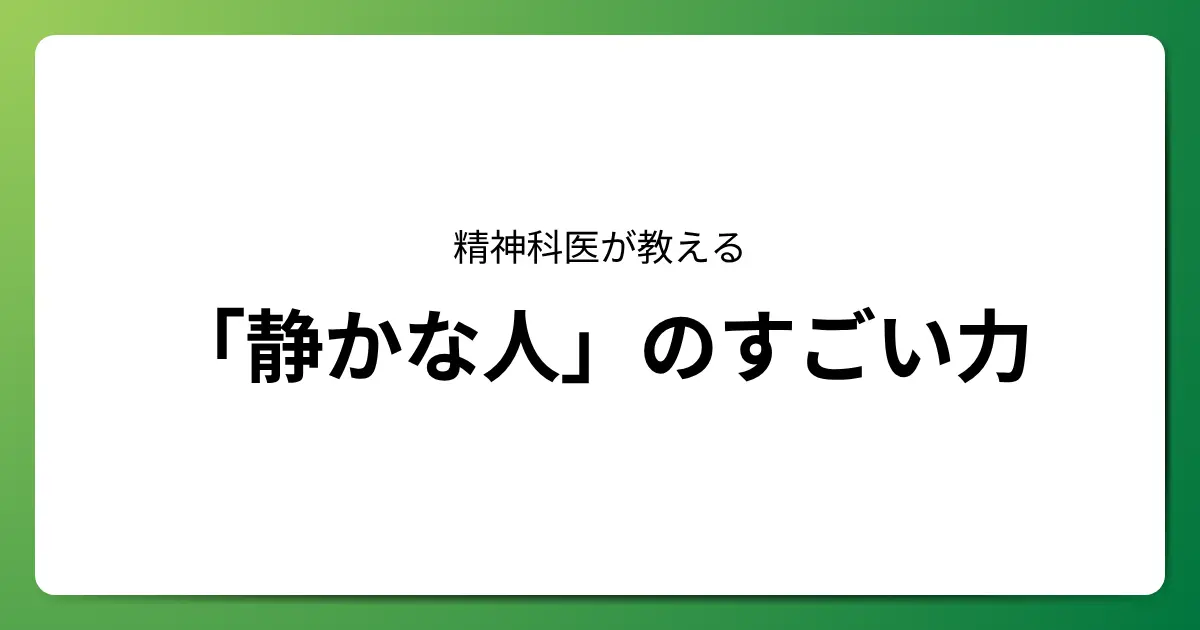この記事は『読書脳 新版・読んだら忘れない読書術』についての書評です。
『読書脳 新版・読んだら忘れない読書術』は、樺沢紫苑さんの著書。
2023年にサンマーク出版から出版されました。
「本を読んでもすぐに内容を忘れてしまう……」とお悩みの方におすすめの書籍です。
本の3行紹介
ベストセラーとなった『アウトプット大全』でお馴染み、樺沢紫苑さんの著書。
「読んだら忘れない」をキーワードに、読書を有意義なものにするための方法が詳しく解説されています。
巻末にはおすすめ本の一覧も載っているので、「これから読書に力を入れていきたい!」と考えている人におすすめの一冊です。
- 第1章:なぜ、読書は必要なのか?読書によって得られる8つのこと
- 第2章:「読んだら忘れない」精神科医の読書術 3つの基本
- 第3章:「読んだら忘れない」精神科医の読書術 2つのキーワード
- 第4章:「読んだら忘れない」精神科医の読書術 超実践編
- 第5章:「読んだら忘れない」精神科医の本の選択術
- 第6章:早く、安く、たくさん読める究極の電子書籍読書術
- 第7章:「読んだら忘れない」精神科医の本の買い方
- 第8章:精神科医がおすすめする珠玉の31冊
個人的な3つの学び
本書を読んで得た、個人的な学びポイントを3つまとめます。
ストレス解消にはコーヒーよりも読書がおすすめ
イギリスのサセックス大学で行われたストレス解消についての研究では、読書、音楽視聴、1杯のコーヒー、テレビゲーム、散歩、それぞれのストレス解消効果を、心拍数などをもとに検証したそうです。
その結果は以下の通りで、読書が一番効果が高かったのだとか。
- 読書:68%
- 音楽視聴:61%
- コーヒー:54%
- 散歩:42%
- テレビゲーム:21%
さらに、静かなところで読書をすると、わずか6分間でストレス解消効果(心拍数減少、筋緊張の落ち着き)が得られることが明らかになっています。
読書によるストレス解消には、即効性があるんですね。
最も効果的な記憶術は複数回のアウトプット
本書によれば、最も効果的な記憶術は「最初のインプットから7~10日以内に3~4回アウトプットする」ということ。
短い期間で繰り返し記憶を思い返すことで、脳にその情報の重要性を伝え、長期記憶として保管させるというわけですね。
特に、樺沢紫苑さんの場合は、以下の要領で1回の読書につき4回アウトプットしているのだとか。
アウトプットというと、どうしても文字で書き記すイメージがありますが、マーカーで線を引いたり、人に話したりするだけなら、すぐにでもできそうですね。
感想を書くのが難しい場合のおすすめ方法
感想を書くのが難しいと感じる場合は、読んだ本の中から心に響いた一文を抜き出し、そこにコメントをつけて紹介するのが良いとのこと。
本全体の感想を書くのはハードルが高いですが、本の中の一部分だけであれば、思ったことを書きやすいと思います。
SNSの文字数上限を考えても、できるだけ短い方が書きやすいですもんね。
私も試してみようと思います。
感想
読書内容を忘れにくくするテクニックがまとめられた本でした。
筆者の『読んだら忘れない読書術』の新版ということで、旧版から多少追記・修正がされています。
前半部分は本書のメイン部分であり、科学的観点&筆者の実体験を交えつつ、「読んだら忘れない」読書術を色々と解説してくれています。
後半部分は、どちらかというとおまけ的な内容で、本の選び方や電子書籍・オーディオブックの活用法について記載されていました。
本を読む習慣がない人には参考になるかもしれません。
一方で、巻末のおすすめ本のリストは一読の価値ありです。
筆者がおすすめする珠玉の本が31冊紹介されていることに加え、難易度のマークや紹介文も併記されているので、次に読む本を探す参考になりました。
本書には読書のメリットも豊富に記載されているので、読書習慣の無い方にはもちろん、「本は読むけれど読み終わったら忘れてしまう」とお悩みの方にもおすすめです。
ただし、筆者の『アウトプット大全』を読んだことがある方にはいくつか重複する内容も含まれているので、事前にパラパラと内容を確認してみたほうがいいかもしれません。
まとめ
この記事では、樺沢紫苑さんの著書である『読書脳 新版・読んだら忘れない読書術』の概要と感想をご紹介しました。
せっかくある程度の時間をかけて本を読むのであれば、できるだけ有意義な体験にした方が良いと思います。
「読み終わったのに、何も思い出せない……」となっては勿体無いので、本を読んだあとはちょっとしたことでも良いので、何かしらアウトプットしてみましょう。
小さな行動を積み重ねていくことで、そのうち自然と感想も書けるようになるはずです。
アウトプット中心の読書習慣を身につけていきたいですね。