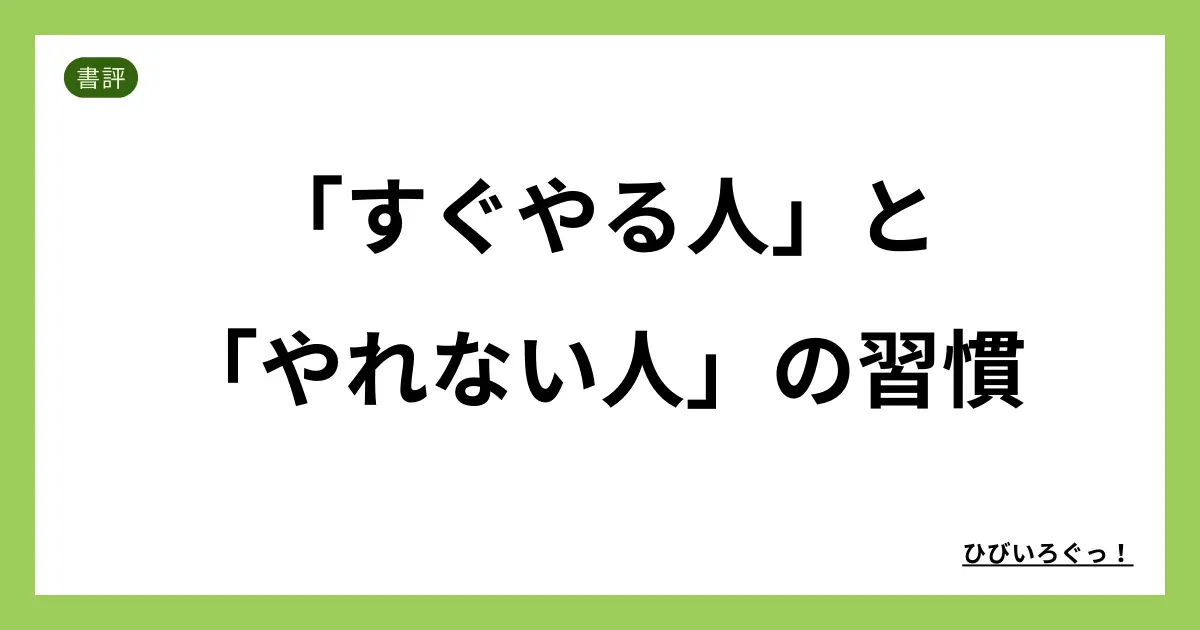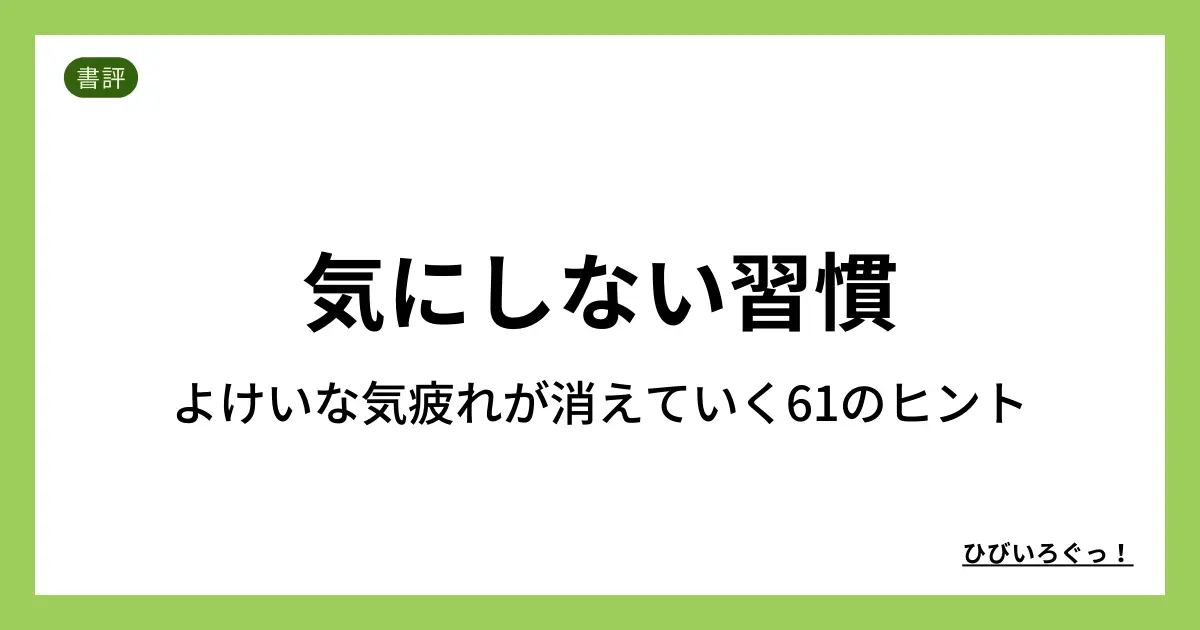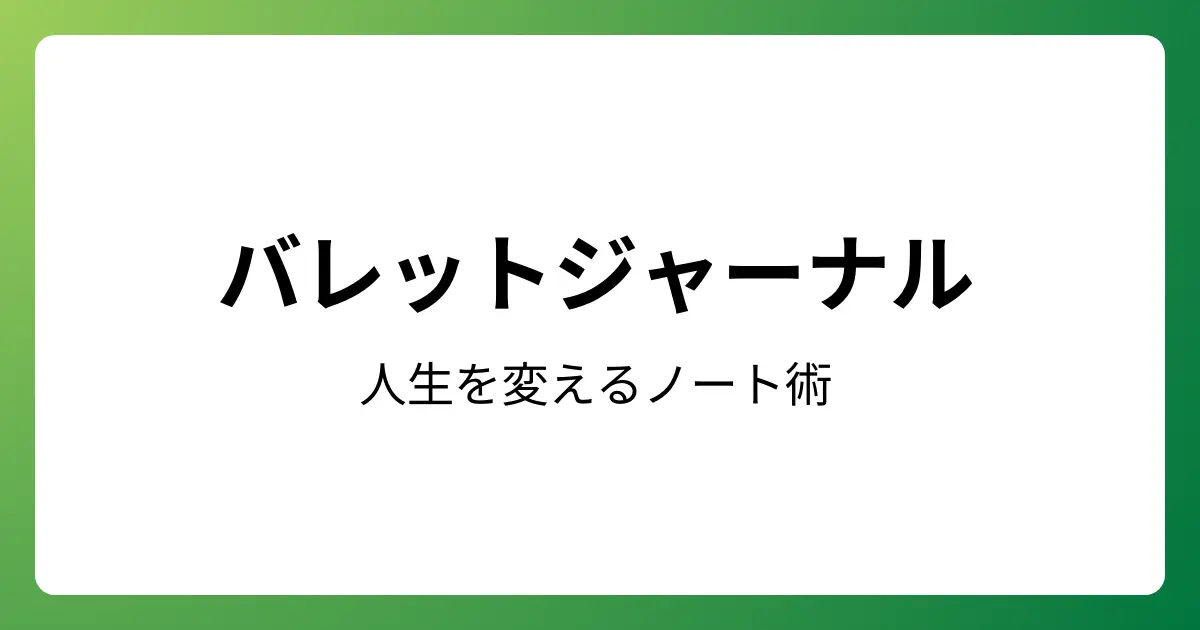この記事は『「すぐやる人」と「やれない人」の習慣 』についての書評です。
『「すぐやる人」と「やれない人」の習慣』は、グローバルリーダー育成に定評のある塚本亮さんの著書。
2017年に明日香出版社から出版されました。
1項目が4ページにまとまっていて隙間時間にも読みやすく、習慣化を学ぶ最初の1冊として優れた良書です。
本の3行紹介
本書は、ケンブリッジ大学やロンドン大学などに多数の合格者を送り込んでいる塚本亮さんの本。
考え込みすぎて行動できない人に向けて、「すぐやる人」になるための習慣が50個紹介されています。
塚本さんご自身の実体験や指導経験に基づいており、机上の空論だけではない、実践的なテクニックが満載です。
- 第1章 思考編
- 第2章 自分を動かす編
- 第3章 周囲を動かす編
- 第4章 感情マネジメント編
- 第5章 体調管理編
- 第6章 時間・目標管理編
- 第7章 行動編
個人的な3つの学び
本書を読んで得た、個人的な学びポイントを3つまとめます。
批判は自身が飛び立つための向かい風
何かに挑戦しようとすると、大抵の場合、どこからか批判の声が聞こえてきます。
そして、挑戦が失敗した途端、「ほら見たことか」としたり顔で言ってくるのです。
しかし、塚本さんは「そもそも人生においては失敗の方が多いのだから、全く気にする必要はない」と述べています。
「失敗」はうまくいかない方法を見つけただけであり、むしろフィードバックをもとに試行錯誤ができるので歓迎すべきものだそうです。
以下の言葉もいいなぁと思いました。
To fly we have to have resistance.
マヤ・リン(アメリカの建築家、芸術家)
(飛ぶためには抵抗がなければならない)
実は科学的な言霊の力
日本には「言霊」という概念があります。
言葉には不思議な力が宿っている、というアレです。
実はこれ、心理学の実験でも証明されているのだとか。
リチャード・ワイズマン教授による実験で、以下の現象が観測されたそうです。
- ポジティブな単語を見た被験者は、ネガティブな単語を見た被験者よりも歩くスピードがアップした
- ネガティブな単語を見た被験者は、ポジティブな単語を見た被験者よりもせっかちになった
つまり、人はポジティブ・ネガティブに関わらず、見聞きした言葉の影響を受けるということ。
後ろ向きな言葉ばかりを使っていると、自分自身も消極的になってしまうんですね。
記憶よりも記録を重視
サッカーで世界的に有名な中村俊輔選手ですが、実は高校時代に挫折を味わったことがあるそうです。
その際に役立ったのが「記録をつける習慣」。
中村選手は挫折を経験して以降、自身の動きを必ずサッカーノートにつけて記録しているそうです。
人間の記憶は結構適当で、勝手に記憶を改竄してしまいます。
しかし、ノートに記録をつければ大丈夫です。
自分がやってきたことが明確になるので、自身の振り返りだけではなく、自己効力感にもつながるのだとか。
感想
「すぐやる人」になるための習慣が50個も掲載されているため、誰でも一つや二つは役に立つヒントが見つけられる良書だと思いました。
書籍としての構成面でも、「すぐやる人」と「やれない人」のパターンをイラスト付きで比較しながら解説してくれるので、違いを意識しやすかったです。
さらに、研究結果等のエビデンスも豊富かつ、著者のスクールで実際に成果が出ている方法ばかりなので、一定の信用が置けるところもポイント。
実際に上手くいっている事例があると安心できますよね。
「行動改善」「習慣化」といったテーマを扱うビジネス書は多いですが、本書はイラストも多く、1項目が4ページ構成で完結しているため、隙間時間にも読みやすい良書でした。
気軽に読み返しやすいので、本棚に置いて、辞書的な感じでときどき読み直そうと思います。
まとめ
本書は、色々考え込んですぐに動けない人にとって、実践しやすいヒントが多い良書でした。
長々と解説をするのではなく、端的に習慣のメリットとデメリットを提示してくれるので、非常に分かりやすかったです。
何度か表紙がリニューアルされていることからも、ロングセラーであることが伝わってきます。
本書の使い方としては、目次の気になったところを開いて読むのがおすすめ。
1つの習慣が4ページで構成されていることに加え、図解イラストも大きめなので、2~3分の隙間時間があれば読むことができます。
日常の隙間時間を使って、「すぐやる人」になる第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか?