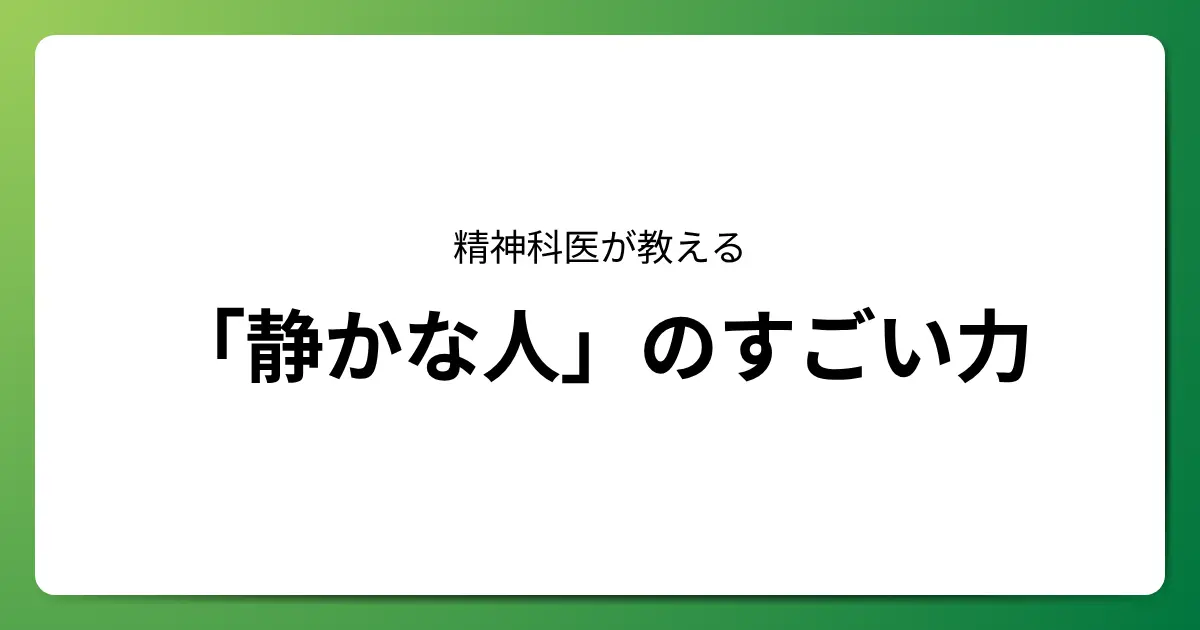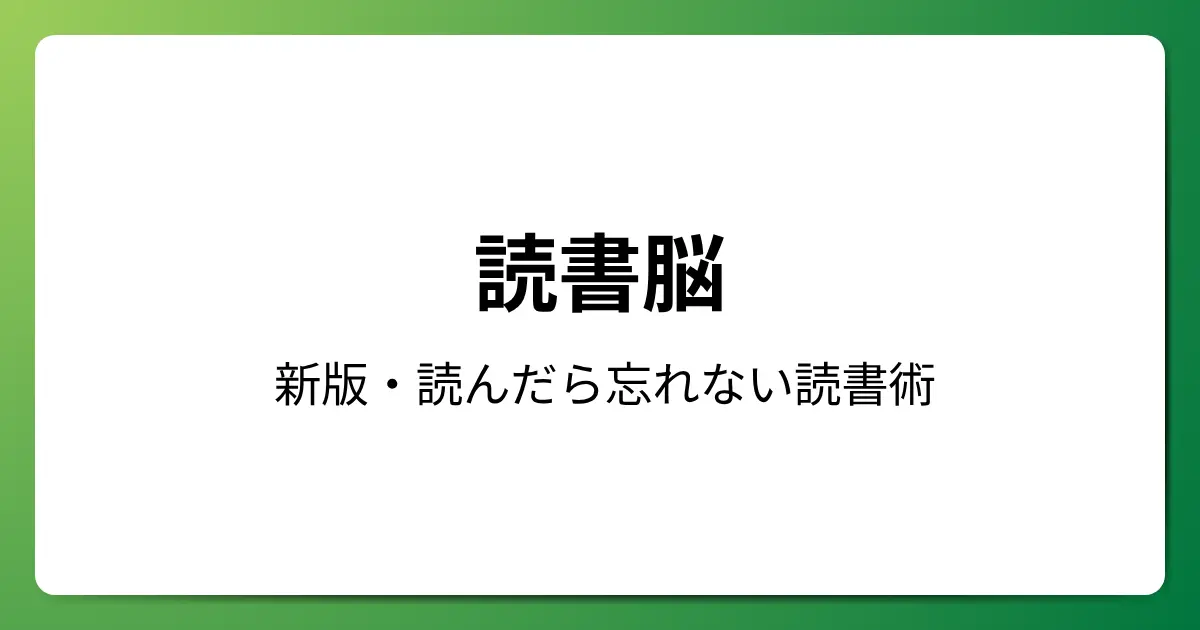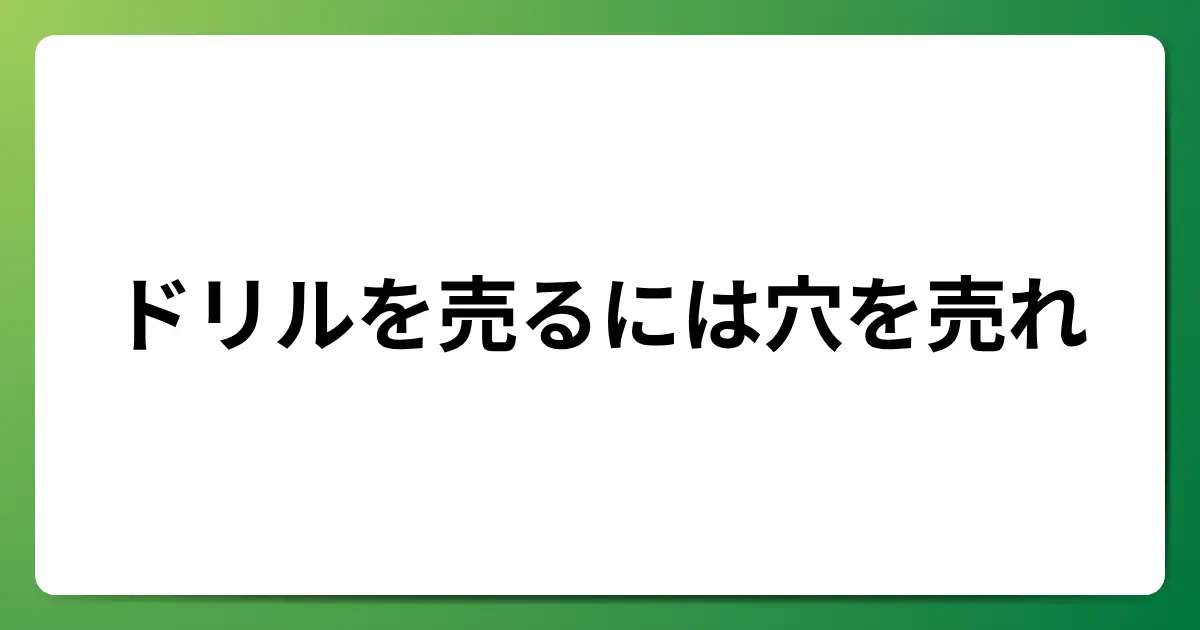この記事は『精神科医が教える「静かな人」のすごい力』についての書評です。
『精神科医が教える「静かな人」のすごい力』は、大山栄作さんの著書。
2024年にSBクリエイティブから出版されました。
「内向的な自分に自信が持てない……」とお悩みの方におすすめの書籍です。
本の3行紹介
アメリカで活躍している内向型の精神科医による本。
自身のこれまでの経験と医学的観点から、内向型だからこその強みを、さまざまな角度から教えてくれます。
内向型の人に自信を持たせてくれるような内容なので、「自分はどうしてこんなに内向的なんだろう……」とお悩みの方におすすめです。
- 序章:なぜ「静かな人」こそ最強の生存戦略なのか?
- 第1章:冷静さ 「静かな存在感」で人を魅了する
- 第2章:思慮深さ 「一目置かれる静かな人」になる
- 第3章:洞察力 静かに瞬時に「本質を見抜く」
- 第4章:客観力 芯のある「静かな生き方」が信頼を生む
- 第5章:独創性 静かな人の脳裏に溢れる「豊かなアイデア」
- 第6章:集中力 外見の静かさと相反する「内面のパワー」
- 第7章:傾聴力 静かに聞いて、「静かな影響力」を発揮する
- 第8章:共感力 「静かな気くばり」で、人の気持ちに寄り添う
個人的な3つの学び
本書を読んで得た、個人的な学びポイントを3つまとめます。
内向型はそもそも身体の作りから異なっている
内向型の人が刺激を避けがちなのは、そもそも遺伝子の影響だそうです。
また、外向型の人と比べて、脳の中に流れる血の量や流れる経路も異なるのだとか。
デブラ・ジョンソン博士による研究結果によると、内向型の人の場合、思考や計画などを司る部位に流れる血液が多かったそうです。
これはそれだけ活発に動いている証拠であり、内向型は深く考えたり、目的に向かって集中したりすることが得意というわけですね。
一方の外向型は、視覚や聴覚などの感覚器官に流れる血液量が多かったようです。
静と動、という感じで面白いですね。
内向型の特徴を活かす「余白」の時間
内向型と外向型は、脳の情報処理のプロセスが異なるそうです。
外向型は最短距離で情報を認識するため、パッと判断して、すぐに行動に移すことができます。
一方の内向型は、入ってきた情報を複数の部位で解釈し、その結果を受けてから行動するため、外向型よりも時間がかかりがちです。
しかし、さまざまな角度から解釈して把握するため、抽象化する力や洞察力に優れているとも言えるとのこと。
この抽象化や洞察力を活かすには、「余白」の時間を作るのをおすすめしています。
組織心理学者のアダム・グラントの実験では、作業前に自由時間を設けた社員の方が創造性の評価が高かったそうです。
もともと創造的な作業が得意な内向型ですから、「余白」の力を借りてその長所を活かせば、より大きな成果を挙げられるかもしれませんね。
感想
内向型に向けた内向型のための本という内容でした。
全編を通して、内向型が自分に自信を持って生きていくための方法がまとめられています。
著者が精神科医ということで、ご自身の経験や科学的根拠をベースに解説されており、なるほどというところも多かったです。
特に、内向型と外向型とでは脳の血液の流れが異なる、という話は初耳で興味深いところでした。
そのほかにも、色々と内向型ならではの強みについて語られており、内向型の自分としては以前よりも前向きに自分を捉えられるようになったと思います。
一方で、ちょっと内向型を賛美しすぎな部分もあるように感じました。
その点を踏まえると、本書は完全に内向型読者に振り切った内容なので、外向型の人にはおすすめできないなと思います。
もしかしたら、「内向型のことを理解したい外向型の人」が読もうとするかもしれませんが、その場合は別の医学書やビジネス書の方が良いでしょう。
逆に、内向型の自覚があって、日々の仕事や生活に何かしらの悩みを抱えている場合は、とりあえず本書を読んでみると良いかもしれません。
まとめ
この記事では、大山栄作さんの著書である『精神科医が教える「静かな人」のすごい力』の概要と感想をご紹介しました。
内向型に振り切った内容なので、人を選ぶ本だとは思いますが、内向的な性格で苦しんでいる方の励みになると思います。
本の内容にすべて納得する必要はないので、「あ、ここは参考になりそうだな」というところを普段の生活に活かしていきましょう。